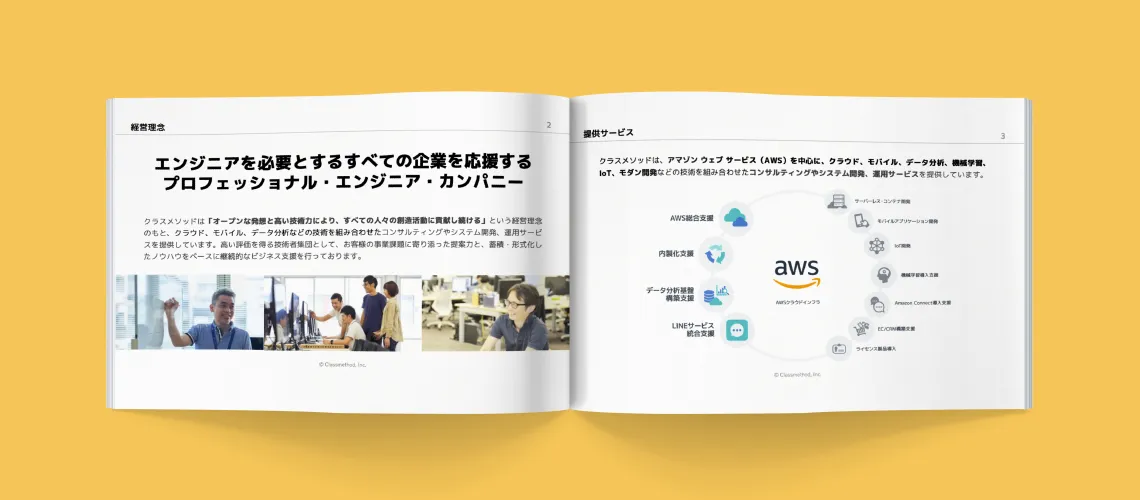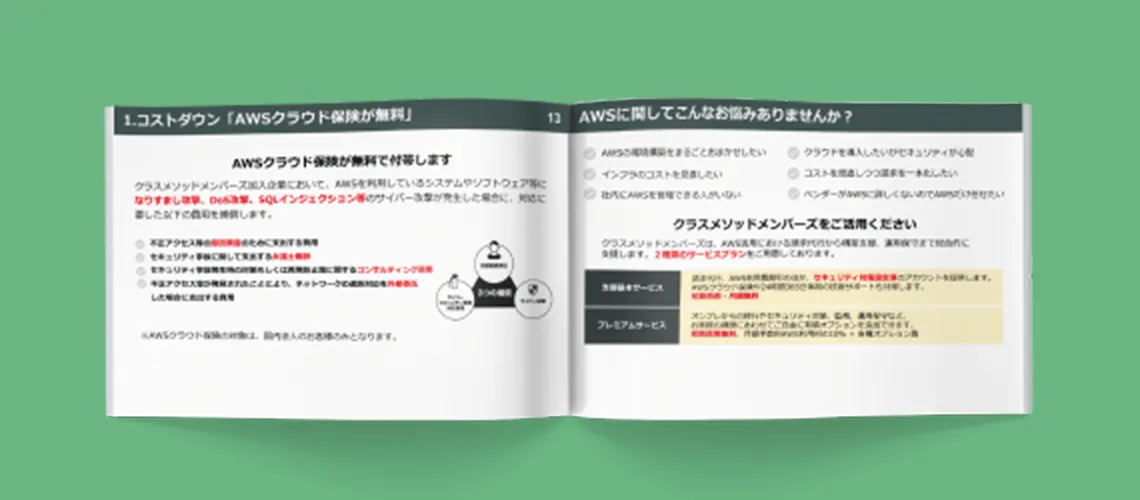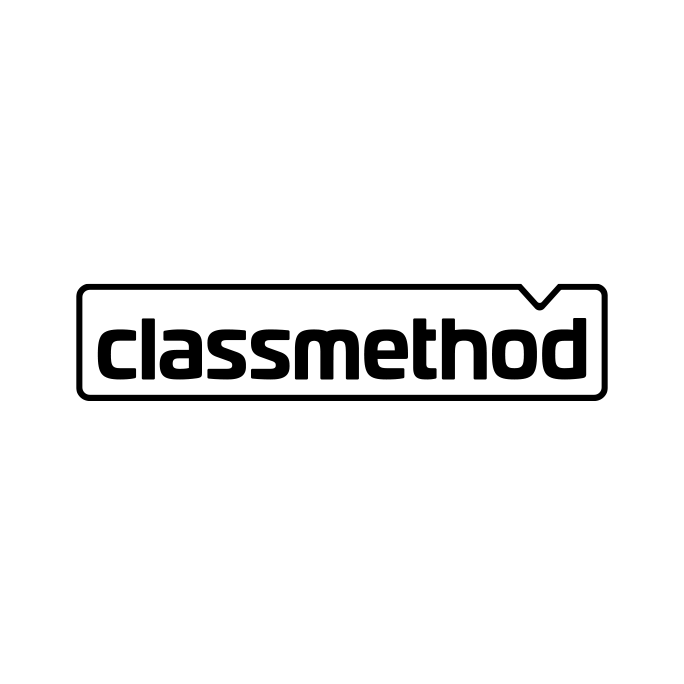1965年に創業し、「青汁」で知られるキューサイ株式会社。誰もが年齢を重ねることを前向きにとらえ、こころ豊かに生きる「ウェルエイジング」を提唱し、「キューサイ青汁」「コラリッチ」「ひざサポートコラーゲン」などお客さまのカラダとココロをサポートするヘルスケア・スキンケア商品の製造・販売事業を展開しています。近年では人気ブランド「コラリッチ」から、美容家IKKOさんが全面プロデュースするコスメシリーズ「BIONIA」や40代以降で加速する肌悩みに寄り添う新シリーズ「コラリッチ ソア」を立ち上げ、事業を拡大し続けています。
同社では、業務改革の一環としてクラスメソッドの生成AIパッケージ「AI-Starter」を導入。クラスメソッドの支援を受けながら、全社員を対象に生成AIの業務活用を進めています。AI-Starter導入と社内のAI活用について、同社IT事業本部情報システム部ITDX推進グループの和才さん、椎野さん、中野さんにお話をうかがいました。
「生成AI活用」と「社内文書の検索」という2つのニーズ
同社ITDX推進グループでは業務改革の一環として、ツールを活用した業務効率化や品質向上に取り組んでおり、ツールの事前検証や運用、他部署との連携などを通じて改善を進めています。そのひとつが、生成AIの活用です。以前はリサーチやアイデア出しといったクリエイティブ業務に一定の時間がかかっており、社内から「生成AIを業務で使いたい」という要望が多く挙がっていたといいます。そこで2023年秋に、もともと取引のあったクラスメソッドにAI活用について相談しました。
「生成AIで何ができるのか、AI導入が会社の売上にどのような形で貢献できるのかなどをクラスメソッドに相談しました。そのなかで、かねてより課題であった社内文書検索が、RAG(検索拡張生成)によって実現可能であることを知りました」(和才さん)

そのため同社では、テレビCMや会報誌などを制作する際、法務部や考査部に「この表現に問題はないか」などの問合せが集中するという業務課題がありました。社内文章を検索できる仕組みがあれば、業務負荷を軽減できるほか、蓄積されたナレッジの活用にもつながります。クラスメソッドのAI-StarterはRAGも導入可能であるため、「生成AIを活用したい」「社内文書を検索したい」という2つのニーズを満たしていました。
「生成AIの導入においては、最新のLLM(大規模言語モデル)を複数使用できることも重視していました。LLMごとに強みは異なりますし、さまざまなLLMを試すことで、私たちの業務に合った生成AIを見定めたいという思いもあったのです。この点においても、AI-Starterは要件にマッチしていると判断し、最終的に導入に至りました」(中野さん)
活用事例の周知や社内イベントで生成AI活用を浸透させる
クラスメソッドは2024年3月にAI-Starterを構築し、同時にRAGの導入も行いました。AI-Starterの正式リリース前には、1ヵ月のテスト期間も設けられました。
「社内から『AIを使ってみたい』という有志を募り、それぞれの部署で業務に生成AIを使用してもらいました。1ヵ月のテスト期間を通じ、活用方法やメリット・デメリットなどをヒアリングしたうえで、同年5月に全社展開した形です」(和才さん)
AI-Starter導入後、ITDX推進グループで力を入れたのが、全社員に向けた生成AI活用の啓蒙活動です。
 「生成AIに興味がある人だけが使うようでは、AI-Starter導入の意味がありません。生成AIを業務で活用するイメージが湧くように、社内の活用事例をポータルサイトに掲載するなど、現在も発信を続けています。また、座学と実践を交えた生成AI研修も定期的に開催しています」(椎野さん)
「生成AIに興味がある人だけが使うようでは、AI-Starter導入の意味がありません。生成AIを業務で活用するイメージが湧くように、社内の活用事例をポータルサイトに掲載するなど、現在も発信を続けています。また、座学と実践を交えた生成AI研修も定期的に開催しています」(椎野さん)2024年秋には、生成AI活用促進を目的とした独自アプリ『Q’sAI冒険門』をITDX推進グループで立ち上げました。アプリから出されるさまざまな課題を、生成AIのプロンプトを活用してクリアすることで、楽しみながら生成AIを学べるように設計されています。
「同アプリを用いた社員参加型イベントも実施しました。個人ランキングと部門別ランキングを設け、社員同士で声を掛けて競い合いながら実際に手を動かして学び、生成AIの使い道を広げていこうというもので、イベント後は、社員のAI利用率が約1.5倍アップしたことも確認できました」(椎野さん)
また、RAGの精度向上など、使い勝手の改善にも継続的に取り組んでいます。
「RAGの導入当初は、古い情報を元に回答がなされたり、健康食品に関する法律を知りたいのに化粧品に関する法律について回答されたりといった場面も見られました。最終的に、すべての資料に対して1つのRAGを作るのではなく、カテゴリごとにRAGを設けることで、精度を向上させることができました。クラスメソッドには逐一相談に乗っていただき、改善に向けて取り組んでもらいました」(和才さん)
「他にも、画面のレイアウト変更といった細かい要望にも対応してくださいますし、問い合わせにも迅速かつ丁寧に回答いただけるので、とても助かっています。AI-Starterには新たなLLMも次々と組み込まれていきますし、社内からは『もう手放せない』という声もいただいています」(中野さん)
社員の75%が生成AIをフル活用。総務部がアプリを開発した事例も
同社はAI-Starterのログを用いて社内のAI利用率を集計しており、記事執筆時点では利用率が75%に達しています。長期休暇後に利用率が大幅に落ちることもなく、多くの社員が日常的に生成AIを活用していることが伺えます。
 「ITDX推進グループでも、ほぼすべての業務にAIを活用していますね。リサーチや議事録の作成、ローコードツールの開発などにも使っていますし、業務改革の一環で社員にインタビューする際も、AIを活用してインタビュー記事を作成しています」(中野さん)
「ITDX推進グループでも、ほぼすべての業務にAIを活用していますね。リサーチや議事録の作成、ローコードツールの開発などにも使っていますし、業務改革の一環で社員にインタビューする際も、AIを活用してインタビュー記事を作成しています」(中野さん)「AWSなどのクラウドサービスを構築するときにも使っています。設定項目や用語の意味がわからないときに、スクリーンショットを撮影してAI-Starterに貼り付け、『この設定項目は何をするもの?』と質問したりするんです」(和才さん)
また同社では、テレビCMの制作チームでは台本のデータをAIに読みこませ、「この場面でこの言葉が入ることは適切か」「ニュアンスは合っているか」といった確認作業を行って品質向上につなげているほか、採用活動においても、自社が求める人材像やマッチングにおいても生成AIを活用しています。
「アプリを開発した部門もあります。人事・総務部が社内のサークル活動用に会員管理アプリを開発していますし、SCM部でも社内販売向けのECアプリを開発しているんです。IT部門以外でもこうしたアプリ開発に取り組めるのは、AIならではですね」(中野さん)
また、各部門でポータルサイトなどに掲載する画像を生成したり、社員それぞれがユーザーアイコンに使う自画像を生成したりといった活用例もあり、和才さんは「社員がAIを自由に使ってコミュニケーションを図っている」と話します。
「画像生成については、商品画像やバナーを画像生成AIによって内製化できないか、検証も実施しています。業務効率化やコミュニケーション活性化といった成果が生まれるなか、生成AIの活用を売上の向上につなげる動きについても、引き続き検討を続けているところです」(和才さん)
「AI-Starter」の成長と共に、さらなる活用を進めたい
費用対効果を見定めるため、AIの業務活用を限定的な範囲に留める企業も少なくないなか、なぜ同社では全社的にAIを活用し、広く浸透させることができたのでしょうか。その理由について、和才さんは「AIを使うことで、新たな世界を知れたからではないか」と話します。
社内からは「会議の音声から議事録を自動的に生成したい」など、生成AIに対する要望は増え続けており、AI-Starterに対する期待値は高いといいます。
「導入から1年余りが経ち、生成AIの進化が目覚ましいことはもちろん、AI-Starter自体もツールとして成長しているように感じます。今後は対話型のみならず、AIエージェントを活用した業務支援も行えたらと考えています。引き続き、最新のLLMを活用できる環境を提供いただけるとありがたいです」(和才さん)
生成AIによる業務改善にいち早く取り組み、全社への浸透に取り組むキューサイ。引き続き、クラスメソッドは同社の生成AI活用に伴走し、ビジネスに貢献してまいります。