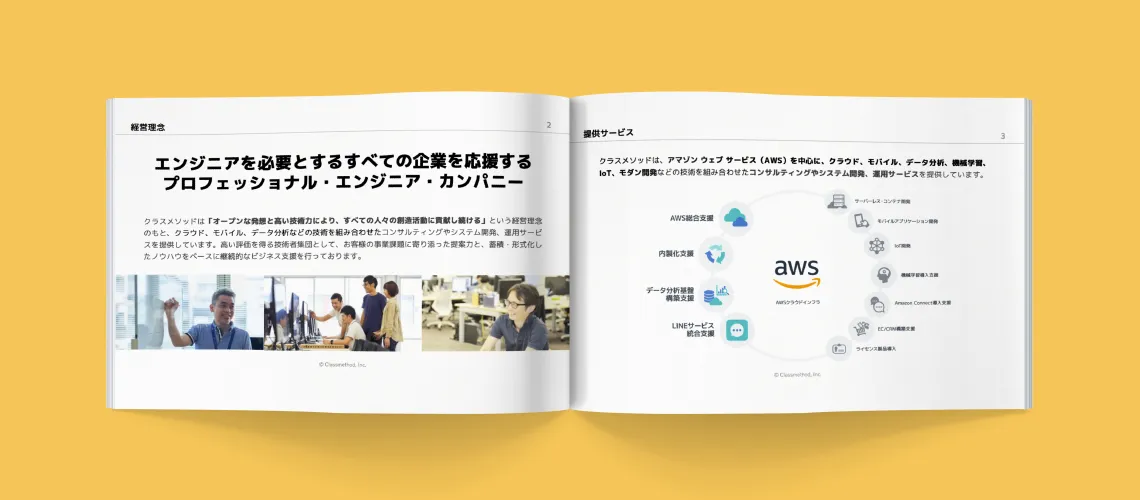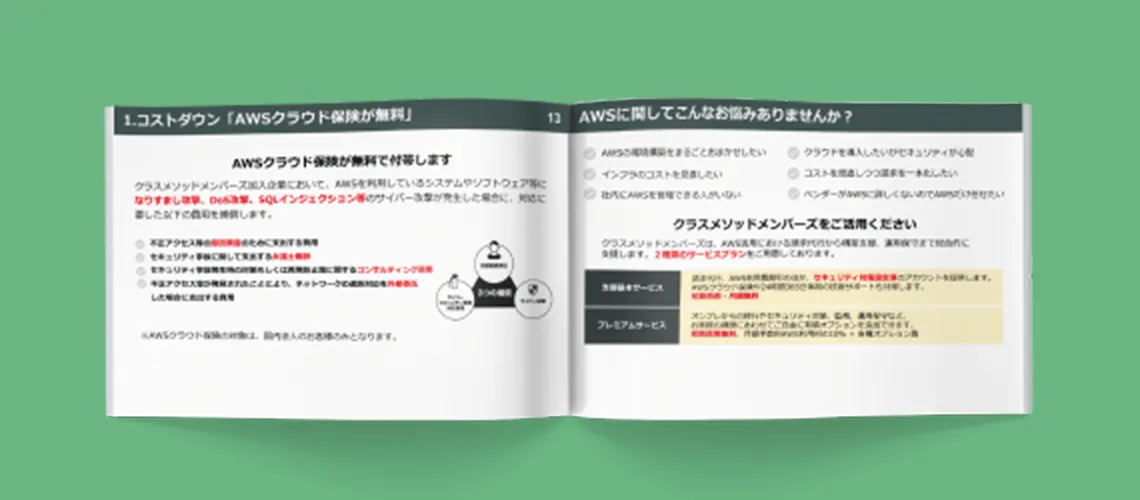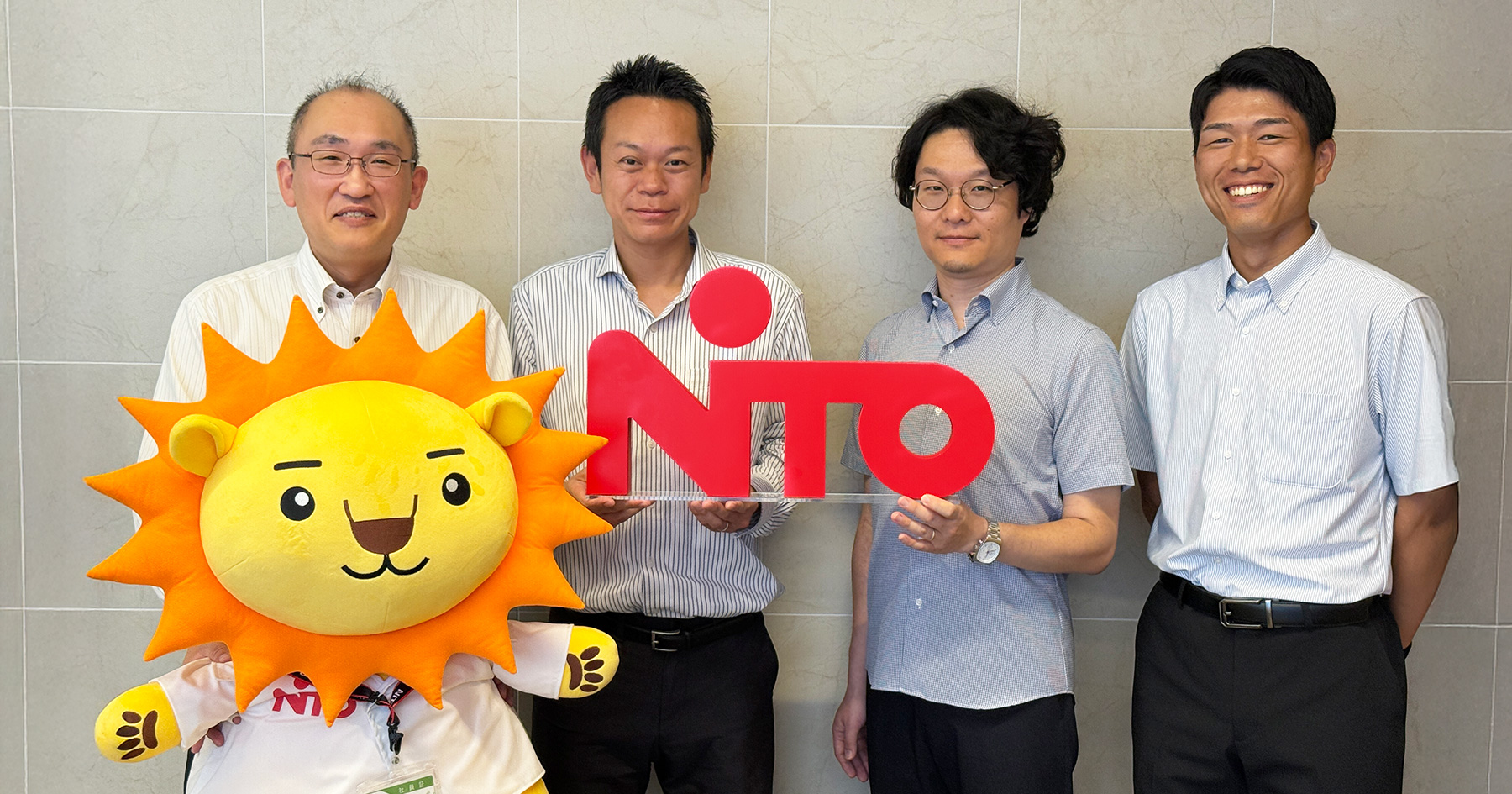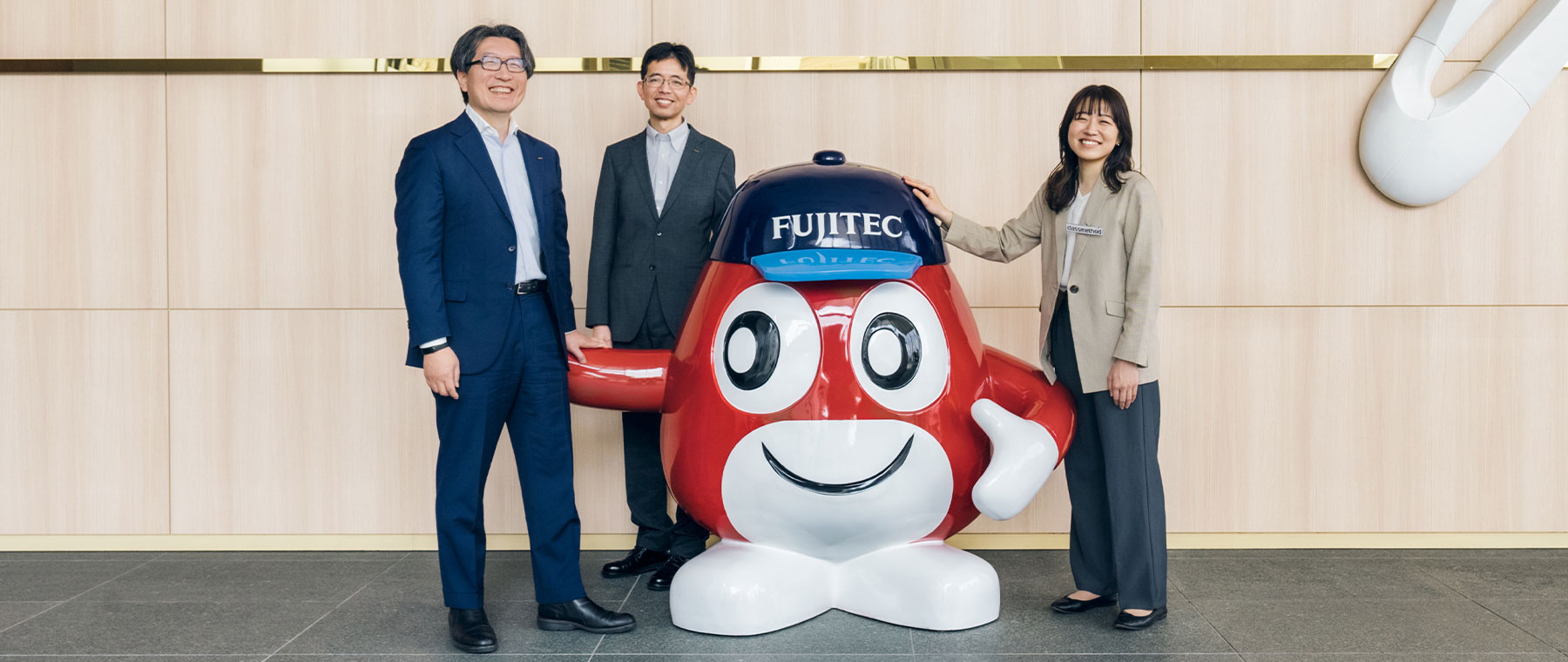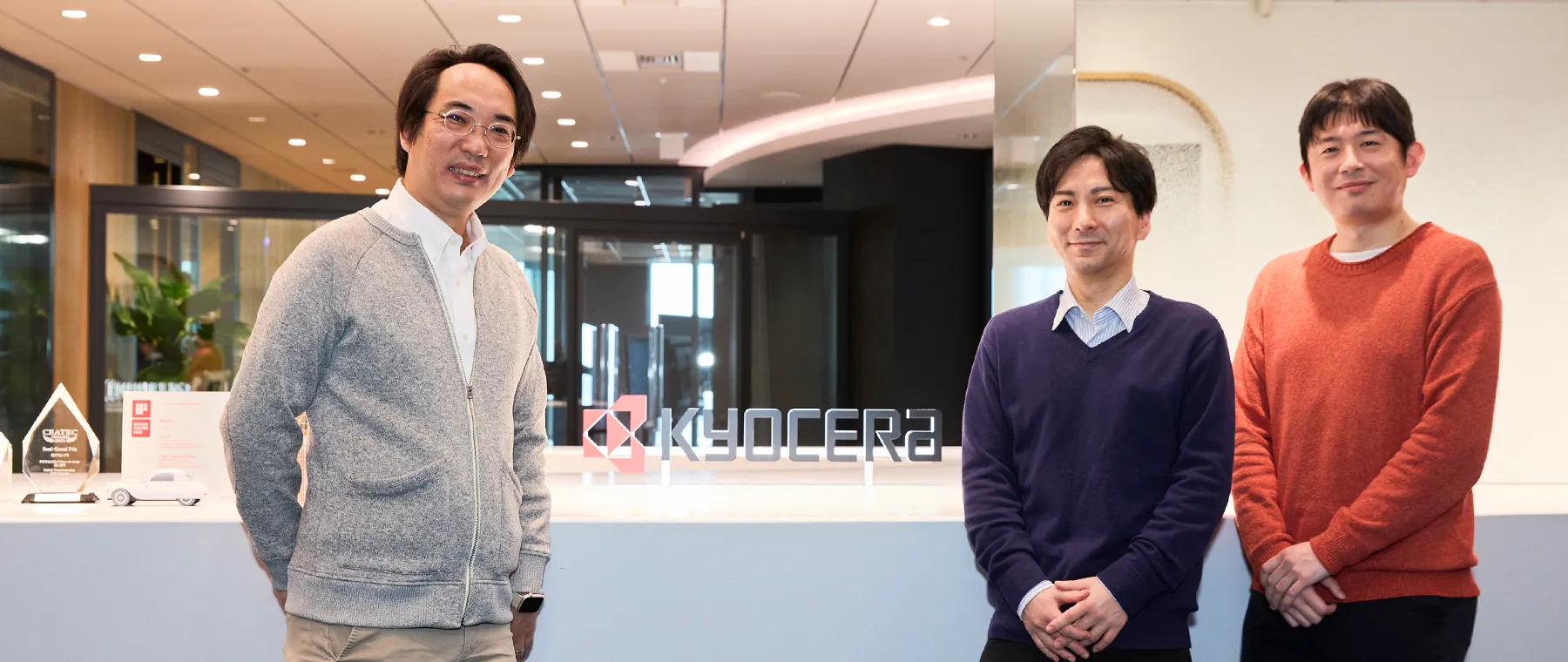1948年に設立した日東工業株式会社は、高圧受電設備や分電盤といった電気設備機器の製造販売を手がける企業です。その製品群は電路システムや通信ネットワークなどあらゆる場面で利用され、私たちの暮らしを支えています。
同社の「お客様相談センター」では、社内外からの問合せに日々対応しています。ただ、問合せから得られた情報が一部共有されておらず、あわせてナレッジの集約や蓄積も課題となっていました。そこで同社では、カスタマーサポートプラットフォームである「Zendesk」を採用。クラスメソッドの支援のもと、約1年かけて段階的な導入を行いました。
Zendesk導入の取り組みとその効果について、カスタマーサポート部の只埜さん・山田さん、配電盤プロセス改革課の野々山さん・吉崎さんにお話をうかがいました。
社内に分散した情報を一元化し、ナレッジの蓄積を図りたい
カスタマーサポート部では、「お客様相談センター」と呼ばれるコンタクトセンター機能を担っており、社内外からの問合せに対応しています。製品を組み込むメーカーをはじめ、代理店やエンドユーザーなど幅広いお客様から問合せがあるほか、社内の営業部門から「お客様から技術的な質問を受けたので教えてほしい」と連絡が来ることも少なくありません。
お客様相談センターでは、社員8名が問合せに対応しており、以前は1日に電話問合せを約100件、メールを約50件受け付けていたといいます。メールでの問合せについては、その内容を収集して、社内へ展開していましたが、電話での問合せについてはそうした仕組みが整っていなかったといいます。
「通話の録音はしていましたが、あくまで電話対応の品質向上などに用いるのみで、情報収集や共有にはあまり活用できていませんでした。また、ベテランの担当者が自身の知見から回答することも多く、業務が属人的になっていたため、今後を考えるとナレッジの蓄積は急務でした」(只埜さん)
さらに、同じような問合せが設計部門などに直接来ることもあり、「問合せ対応に時間を取られて本来の仕事に集中できない」という声も聞かれました。そこで、カスタマーサポート部では、社内に散らばる情報を一元化し、FAQとして公開できる仕組みを構築しようと考えました。
相談を受けたDX推進部は、必要となる要件を整理し、製品の選定を行いました。
「大規模なコンタクトセンターではないため、当初はツールを導入せずにナレッジを蓄積することも検討していました。ただ、社外にも公開すること、スピード感を持って対応できることを考えると、SaaSのカスタマーサービスソリューションが適しているのではと考えたのです。導入するなら機能ごとのオプション購入が不要なオールインワンの製品が安心なのではないか、と只埜と話し、国内でも勢いのあるZendeskが候補に挙がりました」(野々山さん)
「実は、Zendeskはすでに開発部門で活用されており、その導入を担ったのがクラスメソッドでした。実際に開発部門でZendeskのFAQを触らせてもらい、『これはいいな』と手応えを感じましたね。その後、他の調査結果も踏まえて、Zendeskの導入を決めました。開発部門からは、クラスメソッドへの信頼がうかがえましたので、そのままクラスメソッドにお願いすることにしたのです」(只埜さん)
段階的な導入を計画。要望に合わせてツールの追加開発も
同社からの「社内で足固めをしてから社外向けに公開したい」という要望を受け、クラスメソッドではZendeskの段階的な導入を提案しました。
まずPoCを実施し、Zendeskの実現性を確認したあと、フェーズ1として社内版のFAQサイトを構築。その後、フェーズ2では社内向けの問合せ対応(電話・メールの受付およびチケット対応)を導入、フェーズ3では社外版のFAQサイトを構築し、最後のフェーズ4で社外向けの問合せ対応を導入する、という流れです。
「PoCは予想以上にスムーズに進み、正式導入の見通しが立ちました。ただこのとき、『すでに社内に蓄積された大量の情報を、どのようにFAQにインポートするか』という課題も生まれました。Zendeskには、FAQを一括でインポートする機能がなかったのです」(吉崎さん)
当時、社外向けのFAQサイトには200件ほどの記事が公開されていました。カスタマーサポート部ではこれらの情報に加え、この機会に社内に分散した情報を集め、FAQの数を数千件にまで増やしたいと考えていました。
「せっかくFAQを作っても、その中身が知りたいことにヒットしないようでは、誰も使わなくなってしまいます。どんな問合せにも何かしらの回答を提示するには、数千件までFAQの母数を増やす必要があると考えました」(只埜さん)
「FAQを増やすために、過去の問合せ履歴や、WordやPDFで作られた資料などを社内から集め、すべてExcelに整理しました。あわせて、よく問合せを受ける設計・開発部門などにも声をかけ、FAQ記事を作ってもらいました」(山田さん)
こうして集まった大量のFAQについて、クラスメソッドでは専用ツールを別途開発することで、Zendeskへのインポート/エクスポートが可能であると判断し、その旨を同社に提案しました。提案の了承を受け、ツールを開発すると共に、必要となるAWS環境も構築。開発では、実際の動作を同社と確認しながら、細部を調整していきました。
「フェーズ1の社内版FAQサイト構築では、このツールを使い、FAQをCSV形式のファイルからインポートできました。エクスポート機能は、公開後のFAQを一括更新する際に用いています。サイト公開後も、他の部門から数百件単位でFAQが提供されることがあり、その都度まとめてインポートができるので大変便利ですね」(山田さん)
お客様に寄り添い、実現可能性の高い提案を心がける
各フェーズでは、定例会議を毎週実施し、進捗状況を共有しながら導入が進められました。クラスメソッドの対応について、只埜さんは「わかりやすく説明してくれながら進めてくれた」と振り返ります。
「お客様相談センターはベテランぞろいのため、IT用語やツールの操作に慣れていない部署です。こうしたシステム導入は初めてで、会議では専門用語が飛び交うイメージがあったのですが、私たちでもわかる言葉に置き換えて説明してもらえたので、理解が進みました」(只埜さん)
「クラスメソッドには、チケットのエクスポートツールも開発していただきました。Zendeskにもエクスポート機能はあるのですが、担当者が扱いやすいデータ形式ではなかったため、見やすい形で出力できないか相談したんです。こうした相談をしたとき、『できません』と即断するのではなく、『こういうやり方もありますよ』とご提案いただけるので助かりました」(山田さん)
また、FAQサイトのデザインやZendeskの使い勝手についても、成果物を都度確認しながら、修正依頼に柔軟に対応してくれたと評価しています。
「Zendeskは比較的シンプルなパッケージですが、私たちにとってはオーバースペックの部分もあります。そこで、ユーザーが必要なものだけを表示するなど、使いやすさを意識したUIの改善を行いました。『この機能は使わないので非表示にできませんか』など、細かいお願いを何度もできるような関係性を作れたのも、ありがたかったですね」(山田さん)
社内に眠る技術資料をFAQサイトに集約
こうして2025年3月末にフェーズ4が完了。電話やメールによる問合せについて、チケット管理や情報共有の仕組みが実現しました。また、社内外向けのFAQサイトも公開。「これほど早く立ち上がるとは思っていませんでした」と只埜さんは話します。

「他の部署から『この情報をFAQに載せられませんか』と申し出を受けることも増えました。社内に埋もれていた技術資料を再び活かす場所として、FAQが認知され始めていると感じます」(山田さん)
また、ZendeskにはAIアシスタント「Copilot」(旧:Zendesk Advanced AI)を導入。業務効率化に貢献しています。
「通話内容の文字起こしや要約をはじめ、FAQを検索した際のサジェストや、新たなFAQを登録するときの文章生成などに、AIを活用しています。DXを推進する立場としては、これをきっかけに現場でのAI活用が広まればうれしいですね」(野々山さん)
さらに今回のZendesk導入にあたり、カスタマーサポート部ではFAQサイトのPRパンフレットを作成しました。社外のお客様にFAQサイトを活用してもらうことで、自己解決をうながし、問合せ件数を抑制する狙いがあります。
「現場営業の方々も、積極的にパンフレットを配ってくれていますね。私たちとしても、クラスメソッドには要望をいろいろと叶えてもらったこともあり、このFAQサイトには思い入れがあります。こうしたパンフレットを作れたのも、自信を持ってお客様に勧められるものができたからこそでしょう」(只埜さん)
Zendeskの導入は「スタート」にすぎない
今後の展望について、只埜さんは「今回の取り組みはスタートにすぎない」と語ります。
「FAQを構築するだけで満足してしまえば、やがて情報の鮮度が落ち、利用者が離れてしまうでしょう。まずは鮮度を保つためにも、日々新しいFAQを追加し、活性化を図るよう心がけています。そのうえで、今後はVOC (Voice Of Customer)の収集や分析などを通じて、会社の売上に貢献できるような『攻め』の動きもできれば。ここからが、本当の勝負だと考えています」(只埜さん)
「最近では、自分たちでZendeskのマクロを作れるようになり、定型業務をワンクリックで完了できるようにするなど、自発的な業務改善も進んでいます。ただ、今はまだ『業務の効率化』で留まっているのも事実です。その先にある『業務の高度化』を目指し、引き続きクラスメソッドには、質の高い提案をいただけるとありがたく思います」(山田さん)
Zendeskによって業務効率化を図り、さらなる業務高度化への基盤を築いた日東工業。そのゴールに向けて、クラスメソッドは支援を続けてまいります。