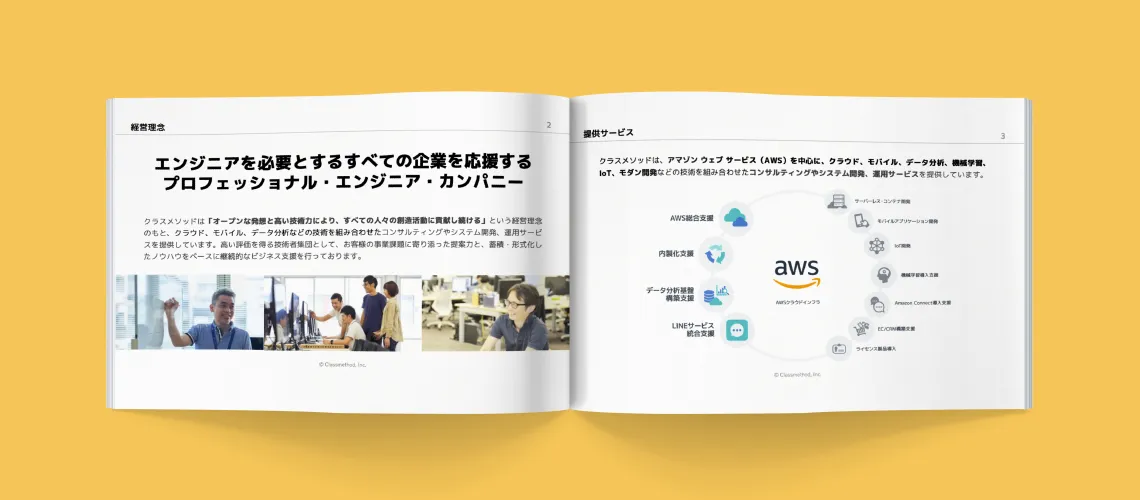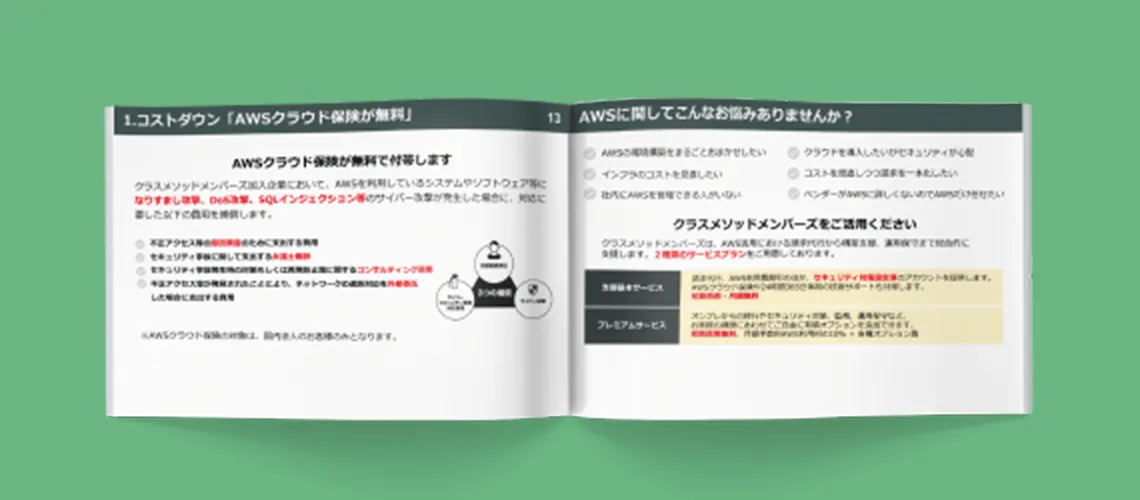企業の技術力や組織文化を社外に伝える「技術広報」。その代表的な取り組みがテックブログです。多くの企業がブログの重要性を認識する一方で、発信内容の質の向上や、レビューをはじめとする運用フロー、担当者の負担増など、継続には多くの課題を抱えています。
 「働く世代に豊かさを」をミッションに掲げ、ロボアドバイザーサービス「ウェルスナビ(WealthNavi)」を提供するウェルスナビ株式会社もまた、同様の課題感がありました。2024年5月にブログのプラットフォームをクラスメソッドが運営する技術者のための情報共有プラットフォーム「Zenn」に変更し、さらにZenn上でテックブログを運営できる有償プラン「Publication Pro」の利用を開始した同社。約1年が経過し、技術広報活動にはどのような変化があったのでしょうか。技術広報を担当されている佐藤祥平さんと、iOSエンジニアとして開発を担当する傍ら、ブログ運営にも参加している長俊貴さんに、導入の経緯から具体的な効果、そして今後の展望まで詳しく伺いました。
「働く世代に豊かさを」をミッションに掲げ、ロボアドバイザーサービス「ウェルスナビ(WealthNavi)」を提供するウェルスナビ株式会社もまた、同様の課題感がありました。2024年5月にブログのプラットフォームをクラスメソッドが運営する技術者のための情報共有プラットフォーム「Zenn」に変更し、さらにZenn上でテックブログを運営できる有償プラン「Publication Pro」の利用を開始した同社。約1年が経過し、技術広報活動にはどのような変化があったのでしょうか。技術広報を担当されている佐藤祥平さんと、iOSエンジニアとして開発を担当する傍ら、ブログ運営にも参加している長俊貴さんに、導入の経緯から具体的な効果、そして今後の展望まで詳しく伺いました。 会社の「中の人」を知ってもらう。その裏側にあった運用コストという課題
同社が技術ブログを運営する最大の目的は、サービスの裏側にある開発組織のリアルな姿を社外に伝えることでした。サービス名が広く認知されていく一方、どのようなエンジニアが、どのような想いで開発に取り組んでいるのかという「中の人」の情報は伝わりにくいと感じていました。特にウェルスナビのサービス領域である金融業界特有の「お堅い」というイメージを払拭し、モダンで挑戦的な開発文化が根付いていることを正しく知ってもらう、それが技術広報における重要なテーマでした。
以前利用していたブログサービスでは、運用面に大きな課題を抱えていました。特に深刻だったのが、記事公開前のレビュープロセスです。金融機関として求められる厳格な基準をクリアするため、同社ではチーム責任者などの有識者に加えてCTO、そしてコンプライアンス部門という3段階のレビューフローを定めています。また、従来のプラットフォームには記事にコメントを残す機能がなく、レビュー担当者は修正指示を出すために、該当箇所をチャットツールにコピー&ペーストし、併せてコメントを書き込むという転記作業を強いられていました。
このフローはレビュー担当者に負担を集中させ、ボトルネックになっていたといいます。また同一箇所に複数のレビュー担当者から同一のコメントがつくケースもあるなど、効率化が課題となっていたのです。
決め手はレビューコストの抜本的改革。Publication Proへの移行
 レビューという根深い課題を解決するため、同社はブログプラットフォームの移行を決断します。技術コミュニティでの存在感と、執筆・閲覧体験の快適さからZennが有力候補となる中、最終的な決め手となったのは有償版の「Publication Pro」のみに搭載されているレビュー機能でした。ボトルネックとなっていたレビュープロセスを抜本的に改善する可能性を秘めていると感じたそうです。Proプランを利用開始すると、その効果はすぐに現れました。
レビューという根深い課題を解決するため、同社はブログプラットフォームの移行を決断します。技術コミュニティでの存在感と、執筆・閲覧体験の快適さからZennが有力候補となる中、最終的な決め手となったのは有償版の「Publication Pro」のみに搭載されているレビュー機能でした。ボトルネックとなっていたレビュープロセスを抜本的に改善する可能性を秘めていると感じたそうです。Proプランを利用開始すると、その効果はすぐに現れました。「Proのレビュー機能は本当にありがたかったです。プレビュー画面の特定箇所に直接コメントを残せるので、『誰がどこに、どういう指摘をしたか』が一目瞭然になりました。Slackでの煩雑なやり取りはなくなり、レビューの精度も向上しました。書き手にとっても、レビュアーにとっても、ストレスが大幅に軽減されたのを実感しています」(長さん)
また、Zennというプラットフォームが持つ拡散力も、執筆者のモチベーション向上という副次的な効果を生みました。トップページにあたる「Trending」に掲載されれば、自社のドメインだけでは届かない多くのエンジニアに記事を読んでもらえます。Trendingへの掲載には社内からも賞賛が集まり、それが次の執筆へのモチベーションにつながるという、ポジティブな連鎖を生んでいるそうです。
ユーザーの声が早期に形に。Zenn運営チーム「信頼感」という価値
一方、Publication Pro導入当初は金融機関ならではの懸念も浮かび上がりました。意図しない形で記事が公開されてしまうという、情報公開リスクです。
 「会社の名前で記事を出す以上、承認フローを経ていない記事が誤って公開されてしまう事態だけは避けたい」(佐藤さん)
「会社の名前で記事を出す以上、承認フローを経ていない記事が誤って公開されてしまう事態だけは避けたい」(佐藤さん)2024年の11月に行われた情報交換で、この課題をZennチームに相談したところ、迅速な機能追加がなされたと振り返ります。
「2025年2月には『レビュー必須機能』として実装されました。これにより、管理者が承認するまで記事を公開できない制御が可能になり、安心して運用できるようになりました。ユーザーの声に真摯に耳を傾け、プロダクトを改善していくその姿勢に、プラットフォームに対する信頼感が高まりました。何かあっても、まずは相談できる窓口があるという安心感は、以前の運用では得られなかった大きな価値です」(長さん)
また2025年1月にはPublication Pro向けの機能として、PublicationとGitHubの単一リポジトリとを連携させる「GitHub連携機能」がリリース。同社では従来からBitbucket Pipelinesを用いた自動校正システムを構築していたのですが、GitHub連携機能により、この機能を用いた校正が可能となりました。現在は、用語法や内容の事前チェックを、執筆者自身が行えるようになっています。今後、GitHub連携機能を利用するメンバーの増加に伴い、レビューの質と効率はさらに向上する見込みだといいます。
テックブログ運営において、レビューは必要な工程ですが、ブランド棄損を避けるために良かれと入れた多数の赤ペンが、執筆者への心理的な負担になるケースも多々あります。執筆者はシステムからのフィードバックにより、負担なく記事の品質を高められ、レビュー担当者は本質的な内容の確認に集中できるという、理想的なサイクルを実現できます。
ブログがきっかけで入社も。着実に広がる技術広報の成果
Publication Proという強力な基盤を得て、同社の技術広報は新たなフェーズへと進んでいます。同社では具体的なKPIや執筆ノルマを設けるのではなく、あくまで緩やかな継続を重視しています。そうした中でアドベントカレンダーのような企画を機に、これまで筆を執らなかったメンバーが参加するなど、自発的な情報発信の文化が根付きつつあるといいます。
そして、その成果は採用活動においても具体的な形で現れ始めています。
「我々のサイバーセキュリティに関するZennの記事を読んで興味を持ち、自主応募をしてくれた方がいました。選考プロセスを経て入社してくれて、現在も活躍してくれています。彼が最近書いた記事もZennでTrendingに掲載されました。こうした良い循環が生まれているのは嬉しいですね」(佐藤さん)
事業の成長と共に、進化し続ける情報発信へ
同社は今後、中核であるロボアドバイザー事業に加え、お客様の人生におけるお金の悩みをトータルにサポートする「総合アドバイザリープラットフォーム」の構築を加速させていきます。事業が多角的に成長していく中で、同社の技術やカルチャーを発信していくことの重要性が、ますます高まっていくのは間違いありません。最後に、これからの情報発信を支えるパートナーとしてのZennへの期待を伺いました。
「Zennには、これからも技術情報発信のプラットフォームとして、業界をリードし続けてほしいと願っています。管理者権限の強化など、さらに強化してほしい機能はあり、ますます進化していってほしいです」(長さん)
クラスメソッドは、今後もZennを通じてウェルスナビの技術広報活動を引き続き支援して参ります。
WealthNavi Engineering Blog
https://zenn.dev/p/wn_engineering