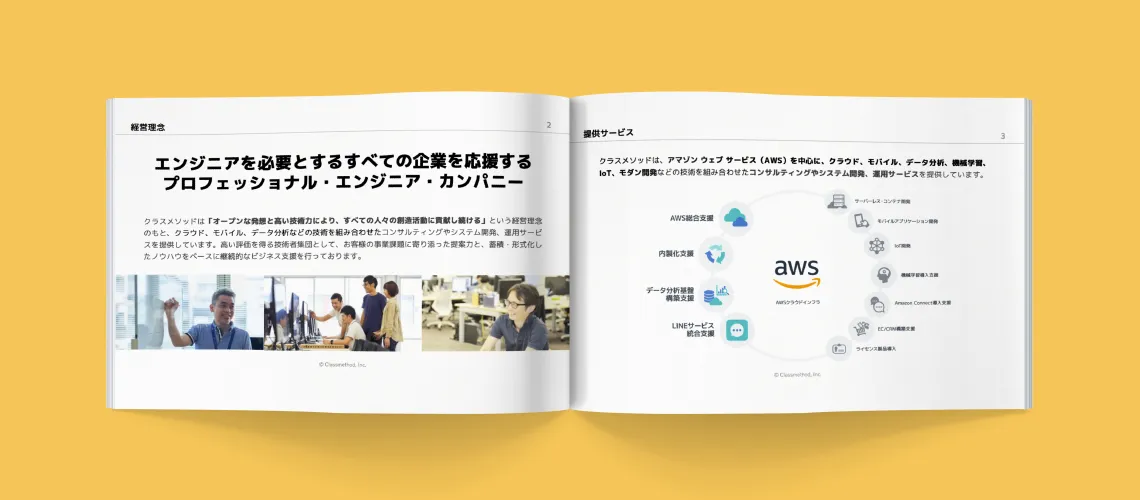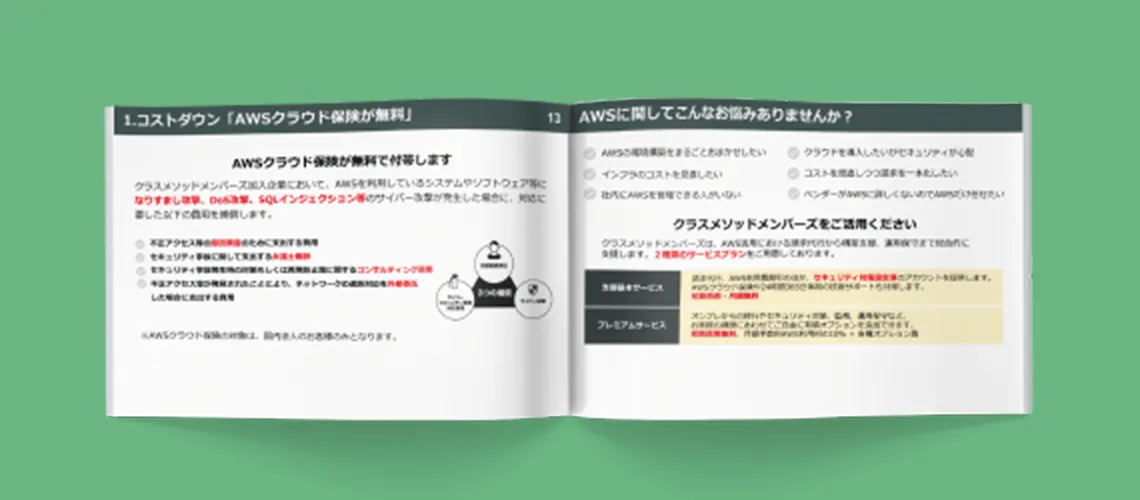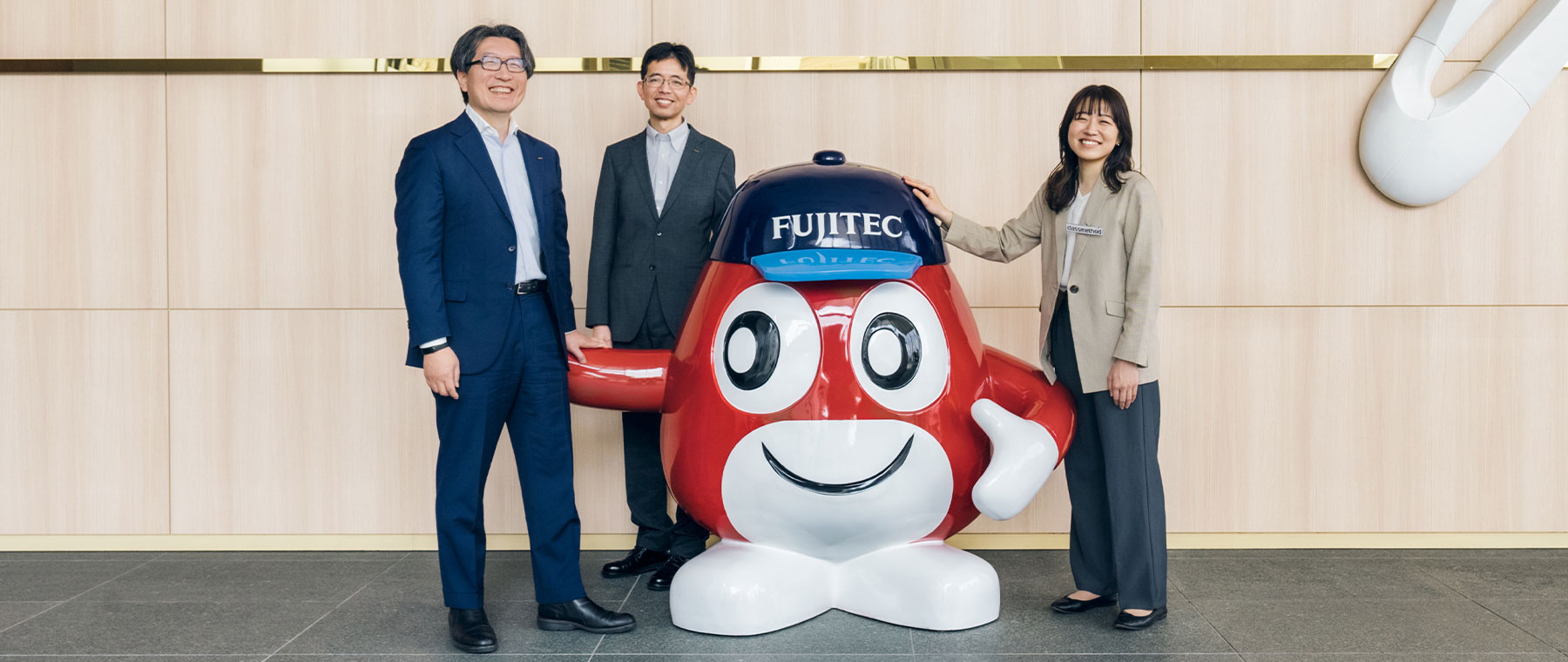ID統合管理を中心としたDXソリューションを提供するコンテンツデータマーケティング(以下、CDM)。同社は主力製品である会員認証サービス「Uniikey(ユニーキー)」のリニューアルにあたり、AWSによる環境構築、およびAmazon QuickSightによるダッシュボード作成に関する技術支援をクラスメソッドに要請しました。Uniikeyリニューアルの経緯とプロジェクトについて、営業本部 本部長 兼 ソリューション本部 本部長の宮本さんと、ソリューション本部 副本部長の鹿島さん、製品開発部の平尾さんにお話をうかがいました。
コンテンツビジネスを支える会員認証サービス「Uniikey」
CDMは、株式会社講談社、TOPPAN株式会社、株式会社CARTA COMMUNICATIONSの3社により2020年に設立された合弁会社です。マーケティングDXで「コンテンツ×ファン」ビジネスの拡大に貢献することを目指し、主力製品として会員認証サービス、いわゆるCIAM(ID統合&アクセス管理)ソリューションの「Uniikey」を提供しています。
 「企業内で複数のサービスを運営する場合、各サービスごとに会員基盤が分散してしまうケースがございます。分散した会員基盤では、運用コストの増加や、利用者に複数のID登録を求めることでユーザー体験(UX)の低下など、さまざまな課題が生じます。 一方で、統合ID基盤をゼロから構築することは、新たに開発リソースや運用保守のコストといった課題を引き起こす可能性があります。これらの課題を解決すべく、マルチテナント対応の統合ID基盤を迅速に導入可能とする「Uniikey」を開発しました。」(宮本さん)
「企業内で複数のサービスを運営する場合、各サービスごとに会員基盤が分散してしまうケースがございます。分散した会員基盤では、運用コストの増加や、利用者に複数のID登録を求めることでユーザー体験(UX)の低下など、さまざまな課題が生じます。 一方で、統合ID基盤をゼロから構築することは、新たに開発リソースや運用保守のコストといった課題を引き起こす可能性があります。これらの課題を解決すべく、マルチテナント対応の統合ID基盤を迅速に導入可能とする「Uniikey」を開発しました。」(宮本さん) Uniikeyのリリースから5年以上が経った現在、提供先は出版社以外にも拡がり、観光庁が推進する観光DXのマーケティング強化モデル実証事業である「天王洲地域CRM構築事業」の顧客ID統合基盤や、東京のローカルテレビ局「TOKYO MX」の視聴者向け会員サービス基盤など、幅広い業種業態に採用されています。
Uniikeyの特徴は、大企業向けのCIAMソリューションと比較して安価に導入できることで、中堅・中小企業においても選択肢となります。また、認証・認可機能だけに留まらず、プライバシーデータ管理や同意管理などの機能もひととおり装備しています。
「Uniikey」をAWSによるフルスクラッチ開発でリニューアル
2020年の初期リリース以来、UniikeyはITベンダーのSaaS型顧客データ管理基盤を通して提供してきました。しかし、一定の制約があるSaaSでは開発の柔軟性に欠け、多様化するユーザーニーズに応えることができません。そこで開発の自由度を高めるべく、Uniikeyの運用基盤をフルスクラッチで再構築することを決断しました。
「ベンチャーである私たちは、ユーザーにあわせてUniikeyを常に進化させていく必要がありますが、既存のSaaSを利用し構築した環境では限界があります。幸い、社内には技術力の高いスタッフが揃っていますので、より使い勝手のいい、高品質のID管理基盤を自社開発することにしました」(宮本さん)
 新Uniikeyで求める機能実装や社内のスキルセット、開発環境などの関係からAWS上での運用を目指した同社は、インフラ構築の技術パートナーとしてクラスメソッドを採用しました。
新Uniikeyで求める機能実装や社内のスキルセット、開発環境などの関係からAWS上での運用を目指した同社は、インフラ構築の技術パートナーとしてクラスメソッドを採用しました。「Uniikeyのフルリニューアルは、アプリケーションの設計・開発からインフラ構築まで多岐にわたります。そこでインフラ領域については外部に協力を要請し、私たちはアプリケーションの開発に集中することにしました。そのためにAWSに関する高度な知見を有するベンダーを探した中から、AWS関連の開発実績が豊富で、信頼性の高いクラスメソッドに協力をお願いすることにしました」(鹿島さん)
将来的な拡張性を確保しインフラ管理の効率化と信頼性の向上を実現
新Uniikeyの開発は、2023年9月から2024年4月までの約8カ月間で実施。クラスメソッドの支援を受けながらアーキテクチャを設計し、コンテナやマネージドサービスを活用したインフラを構築しました。効率的なインフラの構築・管理に向けて、Terraformを導入してIaC化を実現したほか、Github Actionsを活用したCI/CDパイプラインを構築し、コンテナイメージのビルドからデプロイまでを自動化しています。さらにセキュリティ・ガバナンスの観点からマルチアカウント設計とし、AWS Control Towerを用いたアカウント管理環境を構築しました。
「インフラについては保守・メンテナンスの負荷を減らしたいという思いから、クラスメソッドと相談しながらコンテナを中心としたアーテクチャを設計し、IaCやCI/CDパイプラインを積極的に採用しました。プロジェクトはアジャイル的に進め、クラスメソッドのエンジニアと随時ディスカッションを重ねながら、ベストなインフラ基盤を目指しました」(鹿島さん)
 「クラスメソッドには私たちの要望を採り入れた環境を構築していただき、非常に助かりました。結果として私たちはアプリケーションの開発に注力でき、短期間で新Uniikey基盤の構築を終えることができました。私自身もプロジェクトを通して、クラスメソッドの専門知識の高さ、実行力、フォロー体制の手厚さには感銘を受けました」(平尾さん)
「クラスメソッドには私たちの要望を採り入れた環境を構築していただき、非常に助かりました。結果として私たちはアプリケーションの開発に注力でき、短期間で新Uniikey基盤の構築を終えることができました。私自身もプロジェクトを通して、クラスメソッドの専門知識の高さ、実行力、フォロー体制の手厚さには感銘を受けました」(平尾さん) Uniikeyのリニューアル以降、現在は新規ユーザーを取り込みながら、既存ユーザーの移行作業を進めています。柔軟かつスケーラブルな新Uniikeyにより、将来的な拡張性を確保し、インフラ管理の効率化と信頼性の向上を実現しました。
「最大の成果は、市場からのリクエストにスピード感を持って応えられる環境を手に入れたことです。さまざま業界での活用に向けて、マーケットのニーズにフィットした機能やサービスを継続的して提供していく次のステージへの足掛かりができました」(宮本さん)
ユーザー向けダッシュボードの作成支援をクラスメソッドに要請
Uniikeyのリニューアルプロジェクトの過程でクラスメソッドの技術力と業務品質を評価したCDMは、続いてUniikeyのユーザーに提供するAmazon QuickSightを用いたダッシュボードの作成支援を要請しました。
「新Uniikeyのユーザーに、ID会員数の推移を可視化するダッシュボードの提供を構想する中、データソースからの取り込みや加工が容易でシームレスに連携できるAmazon QuickSightに着目しました。それに伴い、ダッシュボード作成におけるコミュニケーションコストを最小限に抑えるためにも、Uniikeyのインフラ基盤やデータ構造を熟知するクラスメソッドに伴走支援をお願いするのがベストと判断しました」(鹿島さん)
ダッシュボードの作成は2024年7月から12月にかけて実施。会員データの構造を分析してAmazon QuickSightに適したデータセットを整備し、Amazon Athenaによるクエリを作成したうえでダッシュボードを構築しました。さらにUniikeyを導入したユーザーの中で、担当者によって表示できるデータに制限をかけるため、Amazon QuickSightの行レベルセキュリティを利用して閲覧権限を設定しています。
「今回、Amazon QuickSightを初めて使うということで、クラスメソッドのエンジニアにアドバイスをもらいながら構築を進めていきました。データソースからの取り込みエラーが発生した場合のリカバリー方法も教えていただき、不測の事態にも耐えられるダッシュボードを作成することができました。プロジェクト中、クラスメソッドからはお互いのコミュニケーションエラーが発生しないように、図を多用しながら背景情報も含めた詳しい説明をいただけたことが印象に残っています。問い合わせの際もさまざまな資料や図版を用意していただき、丁寧な対応に助けられました」(鹿島さん)
「Uniikeyのアプリケーションにダッシュボードを組み込む際、クラスメソッドから技術的な方針や情報提供をいただき、何とかリリースまでたどり着くことができました。初めて利用するAmazon QuickSightやAmazon Athenaに関しても、私たちがダッシュボードを自律的に運用できるようにレクチャーをいただきました」(平尾さん)
ID会員数の推移を直感的に把握できるダッシュボードは、Uniikeyのユーザーに対して新たな付加価値を提供し、ユーザーのサービスの独自性を引き立てるのに貢献しています。
「Uniikeyのユーザーにとって、自分たちのお客様の属性を知ることはほんの入口に過ぎません。そこから分析へと踏みだし、価値あるサービスやコンテンツに発展させていくことが本質的なデータ活用です。ダッシュボードはデータ分析のきっかけになるもので、ユーザーに気付きを得ていただくための一歩を提供することができました」(宮本さん)

企業間を超えたデータコラボレーションの実現を支援
Uniikeyは今後、ID管理製品として、GDPR対応、多言語対応、データ管理機能の強化などに取り組んでいく構想を描いています。さらにその先として見据えているのは、ID管理製品単体としてのサービス提供だけでなく、企業間を超えたデータコラボレーションの実現を支援することです。
「Webマーケティングの世界では、コンプライアンスをクリアしたうえで複数の組織が保有するデータを共有・活用し、自社だけでは得られない新たな価値を生み出すデータコラボレーションに対する注目度が高まっています。日本の各所で実証実験が始まっているスマートシティにおいても、オープンデータやパーソナルデータといったデータの流通は不可欠となっています。数年以内にデータ流通の本格化が始まると予測される中、企業においてはデータの保有自体が競争力の源泉となるはずです。CDMとしてはユーザー同士が安全にデータコラボレーションできるよう、データの価値を高める活動を推し進めていきます」(宮本さん)
「Making all services accessible(すべてのサービスをアクセシブルに)」をミッションに掲げて最新技術の提供に取り組むCDM。クラスメソッドは同社のマーケティングDXを引き続き支援してまいります。