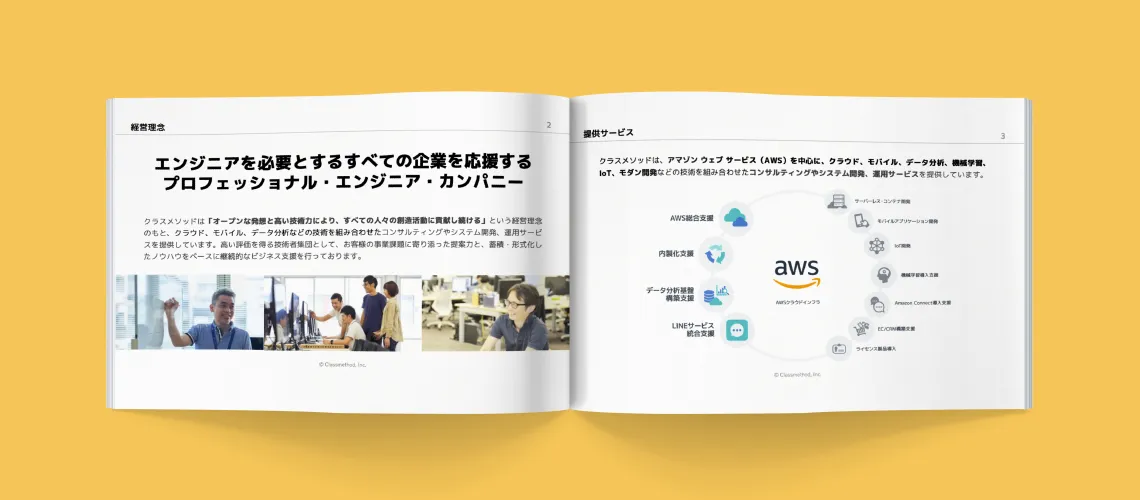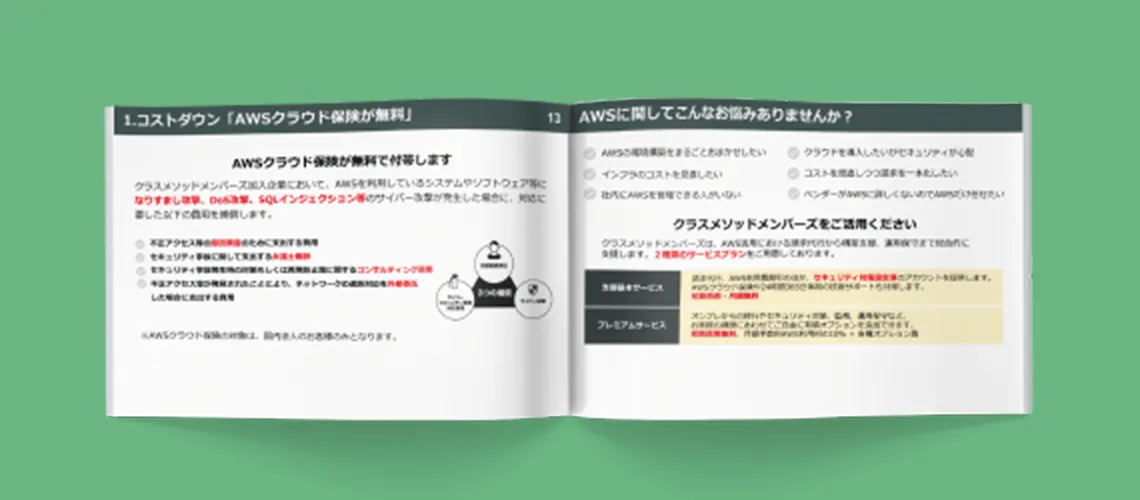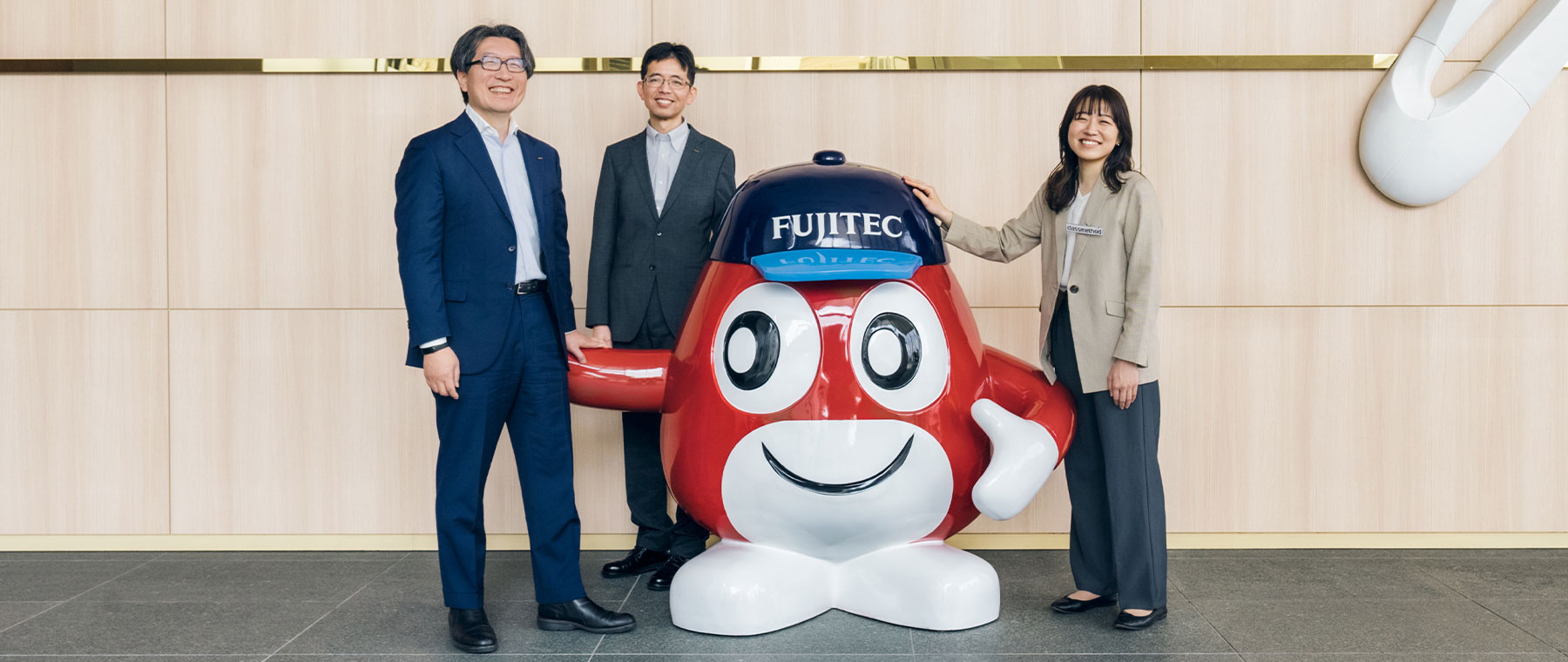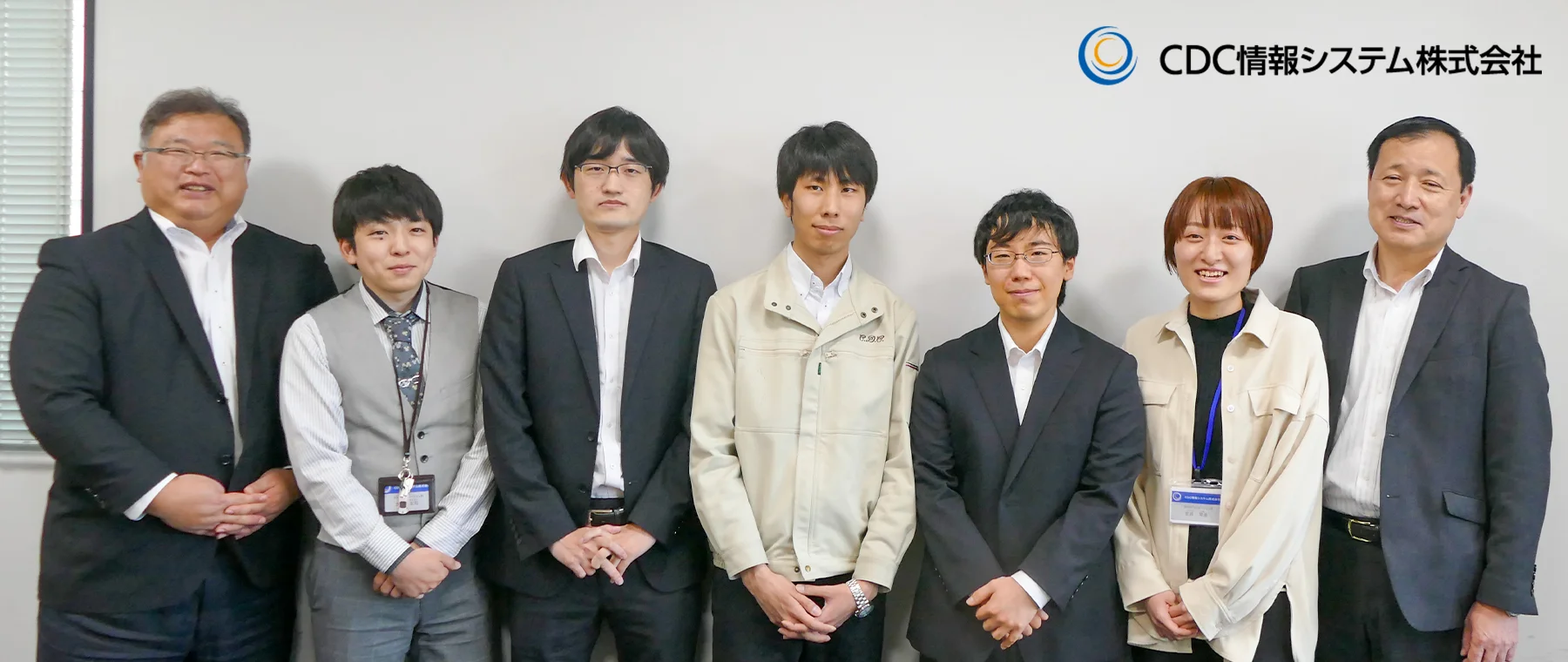FOOD & LIFE COMPANIESの主力事業である回転寿司「スシロー」は、近年アジア地域を中心に海外展開を加速している。ITの基礎部分は日本のものを複製・再利用して各拠点に展開するので、海外でもスピーディーに事業を立ち上げることができる。こうしたシステムのインフラはアマゾン ウェブ サービス(AWS)上で動いている。同社のITをパートナーとして支えているのが、AWSを総合的に支援するサービスを提供するクラスメソッドである。
(※ 本稿は2025年1月に日経ビジネス電子版に掲載された座談会の再掲です)
日本製の基礎に現地の要素を載せて加速するスシローの海外展開
ーーーFOOD & LIFE COMPANIES(以下、F&LC)は様々な飲食系業態を展開していますが、その中核である「スシロー」の海外事業が加速しています。
 小河 海外挑戦の第一歩は韓国でした。2011年に現地法人を設立して事業をスタートしましたが、かなり苦労しました。次に、2017年に台湾に現地法人を立ち上げたのですが、この事業はすぐに軌道に乗り、以後の海外展開が加速しました。現在では中国大陸やタイ、シンガポール、インドネシアなどでも店舗を展開しています。国内のスシローは655店、海外のスシローは174店です。近く、米国とマレーシアにも店舗を開設する予定です。海外スシロー事業は業績への貢献度も高く、営業利益ベースでは国内スシロー事業の半分近くに迫っています(2024年9月期)。
小河 海外挑戦の第一歩は韓国でした。2011年に現地法人を設立して事業をスタートしましたが、かなり苦労しました。次に、2017年に台湾に現地法人を立ち上げたのですが、この事業はすぐに軌道に乗り、以後の海外展開が加速しました。現在では中国大陸やタイ、シンガポール、インドネシアなどでも店舗を展開しています。国内のスシローは655店、海外のスシローは174店です。近く、米国とマレーシアにも店舗を開設する予定です。海外スシロー事業は業績への貢献度も高く、営業利益ベースでは国内スシロー事業の半分近くに迫っています(2024年9月期)。クラスメソッド 代表取締役 横田聡 海外事業の成功要因はどのようなものでしょうか。
小河 ポイントは人財育成と寿司の再現性だと思います。日本での味にできるだけ近付けるとともに、店舗のオペレーションや仕組みなど基礎部分については日本のものを現地に持っていき、その上にローカル要素を載せていくというスタイルです。
横田 シャリは日本製、その上のネタは現地製といったイメージですね(笑)。
ーーースシローは先進的なITユーザーとしても知られています。
小河 早い時期から、タッチパネルで注文を受けるといったIT化を進めてきました。寿司を載せる皿の裏に搭載したICチップでデータを収集し、お客様の注文傾向などを分析してきました。そのほかにも、多くの領域でITを活用しています。ITとの親和性の高さは、回転寿司という業態の特性といえるかもしれません。
横田 クラウドを導入した時期も早かったですね。AWS東京リージョンの立ち上げは2011年ですが、スシローさんは2012年からのAWSユーザーです。
ーーースシローとクラスメソッドとの出会いについて教えてください。
 坂口 2013年ごろのことです。当社はAWS上で、皿のICチップで集めた膨大なデータを分析するシステムを動かしています。そのパフォーマンスが上がらず困っていたのですが、クラスメソッドに相談したところ見事に課題が解決しました。
坂口 2013年ごろのことです。当社はAWS上で、皿のICチップで集めた膨大なデータを分析するシステムを動かしています。そのパフォーマンスが上がらず困っていたのですが、クラスメソッドに相談したところ見事に課題が解決しました。クラスメソッド クラウド事業本部 鈴木亮 AWSのインフラとその上で動くアプリケーションの調整を支援いたしました。パフォーマンスが上がらないので、事業成長に合わせてAWSのサーバーの増強を試みられていましたが、私たちがシステムのボトルネックを特定、適切な設定を取り入れていただいたことで、サーバーコストは8分の1に抑制することができました。
坂口 当初は別のベンダーにAWSのサポートをお願いしていたのですが、改めてAWSに相談して紹介されたのが、クラスメソッドでした。
小河 以来、クラスメソッドは頼りになるパートナーです。
システムの複製・再利用で海外展開。初期投資の抑制で進出・撤退が容易に
ーーー海外進出する企業にとって、システムの構築は大きな課題です。
小河 当社の場合、日本と海外の店舗は基本的に同じ形態です。システムも同様なので、日本で実績のあるものを複製・再利用して海外でも動かしています。企業によっては、グローバルで1つの巨大システムを構築するケースもあるでしょう。私たちはそうではなく、日本と同じシステムを各国・地域に展開するというスタイルです。
横田 複製することで立ち上がりも早く、ビジネススピードは格段に向上しますね。同時に、個人情報など一部のデータを除けば、日本本社でグローバルのデータ分析、需要予測などができますし、セキュリティーなどの管理もできます。AWSのメリットを最大限に生かした使い方だと思います。
小河 “複製”というと簡単なようですが、元になる日本のシステムのアーキテクチャを複製可能な状態にしておく必要があります。これが大前提です。
 横田 そのアーキテクチャを実現するのはかなりの大仕事です。新規に構築するなら別ですが、従来型の既存システムは往々にしてプログラムが複雑に絡み合っているので、これを大きく改修する必要があります。システムをいくつかのレイヤーに分けてきちんと整理し、様々なパーツをプラグで抜き差しできるような形にしなければなりません。
横田 そのアーキテクチャを実現するのはかなりの大仕事です。新規に構築するなら別ですが、従来型の既存システムは往々にしてプログラムが複雑に絡み合っているので、これを大きく改修する必要があります。システムをいくつかのレイヤーに分けてきちんと整理し、様々なパーツをプラグで抜き差しできるような形にしなければなりません。小河 クラウドを前提に、拡張性に優れ、かつ短期間で海外市場にも適用できるシステムのアーキテクチャを検討し実現しました。2010年代のことですが、そのときの意思決定が後々に効いてきて、海外進出を含めて、当社のビジネススピードは非常に高まりました。
横田 クラウドではなく、オンプレミスのシステムを海外に展開する場合、現地のデータセンターやシステムインテグレータ、そのインテグレータとの橋渡しをする日本のインテグレータなど多くのプレーヤーの協力が必要です。交渉や契約に時間がかかる上、相当のコストがかかります。クラウドであれば、そのような面倒なプロセスは不要です。
小河 新しい国や地域に進出する際、初期投資を抑えられることはクラウドの大きな魅力です。それは、試行錯誤の促進を意味します。クラウドなら撤退の判断もしやすい。大きな初期投資をすれば、現地ビジネスが低調だったとしても、「あれだけの投資をしたのだからもう少し頑張ろう」と考えがちで、判断のタイミングを逃す可能性があります。また、撤退しやすいがゆえに、積極的な海外展開ができるという面もあります。
専門家のサポートを得ながらAWSの進化のスピードに追随
ーーー先進的なITの構築には、相当数のエンジニアが必要になると思います。
小河 当社の売上高は3611億円(2024年9月期)ですが、情報システム部は比較的小さいと思います。日本本社の部員は14人で、海外の現地法人にはそれぞれ2、3人のメンバーがいます。
坂口 小さな所帯なので、外部のサポートは欠かせません。情報システム部として技術的な知見を求められることは当然ですが、多種多様な技術をそれぞれ深掘りするのは困難です。それ以上に各現場のニーズを知り、現場と協力して解決策を探ることのほうが重要。個々の技術について外部専門家集団の助けを借りながら、解決策を検討・実行するというスタイルです。その中でも、クラスメソッドの存在は大きい。当社を担当している鈴木さんは、AWS上で稼働する当社システムの状況を定期的にモニターし、障害の予兆などがあればすぐに教えてくれます。私が初めて気づかされることも多いですね。
 鈴木 ときどきスシローのシステムの状況を見て、異常値が見つかれば坂口さんにお知らせしています。パートナー企業がお客様のITをモニタリングする仕組みは、AWSの中で提供されています。
鈴木 ときどきスシローのシステムの状況を見て、異常値が見つかれば坂口さんにお知らせしています。パートナー企業がお客様のITをモニタリングする仕組みは、AWSの中で提供されています。小河 以前、お客様に影響のあるアプリケーション障害が発生したことがあります。クラスメソッドの守備範囲ではないのですが、相談したところ、すぐに「こうしたほうがいい」という提案をもらいました。その通りにするとシステムは復旧し、パフォーマンスが向上しました。それとは別の観点ですが、AWSの進化のスピードは速く、高頻度で新サービスが登場しますし、いつのまにか機能拡張が行われていたりします。新しい情報にキャッチアップするだけでも大変ですが、そこはクラスメソッドがきちんと押さえてくれています。
鈴木 AWSの動向は注意深くウォッチしていて、当社技術ブログのDevelopersIOでも都度検証記事をアウトプット。その中でも特に「この技術はスシローで役立つ」と思ったものは個別にお勧めします。「いいネタが入りましたよ」というカンジでしょうか(笑)。採用いただいた場合には、導入支援やAWSへのフィードバックなどのサポートも行っています。
ーーー海外拠点に数人ずつ配置されているIT人財の教育、日本とのコミュニケーションについては、どのような工夫をしていますか。
小河 先日、中国大陸拠点のメンバーを大阪の本社に呼び、日本のメンバーとともに勉強してもらいました。3カ月ほど同じ釜の飯を食い、当社システムの設計思想やアーキテクチャなどを学ぶ形です。お互いの理解が深まりますし、研修期間終了後のコミュニケーションも円滑化します。
ーーー最後に、今後の展望についてお聞かせください。
小河 情報システムに関する現在の主要テーマは、データ基盤づくりとセキュリティー強化です。これらのテーマだけでなく、システムのあらゆる面において、クラスメソッドのサポートに期待しています。
横田 スシローさんにはAWSを軸にサービスを提供してきましたが、そのエリアも徐々に広がってきました。日本企業が積極的に海外進出し、現地の人たちから喜ばれているというのは、そのシステムを支える私たちにとっても嬉しいことです。当社としては、ITで競争力向上を目指す企業を、今後とも全力で支援していきたいと考えています。